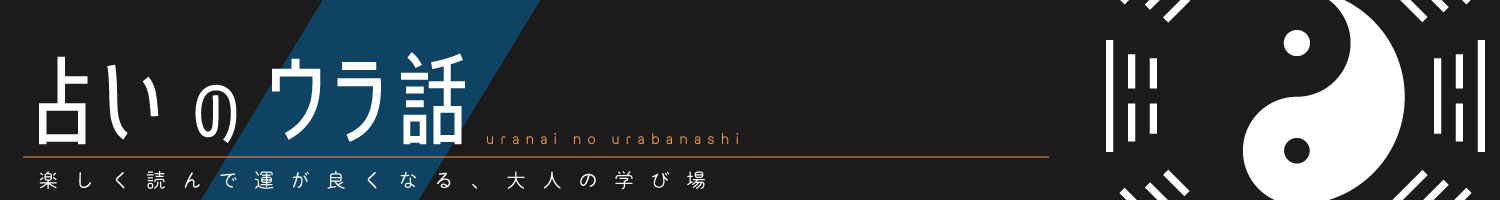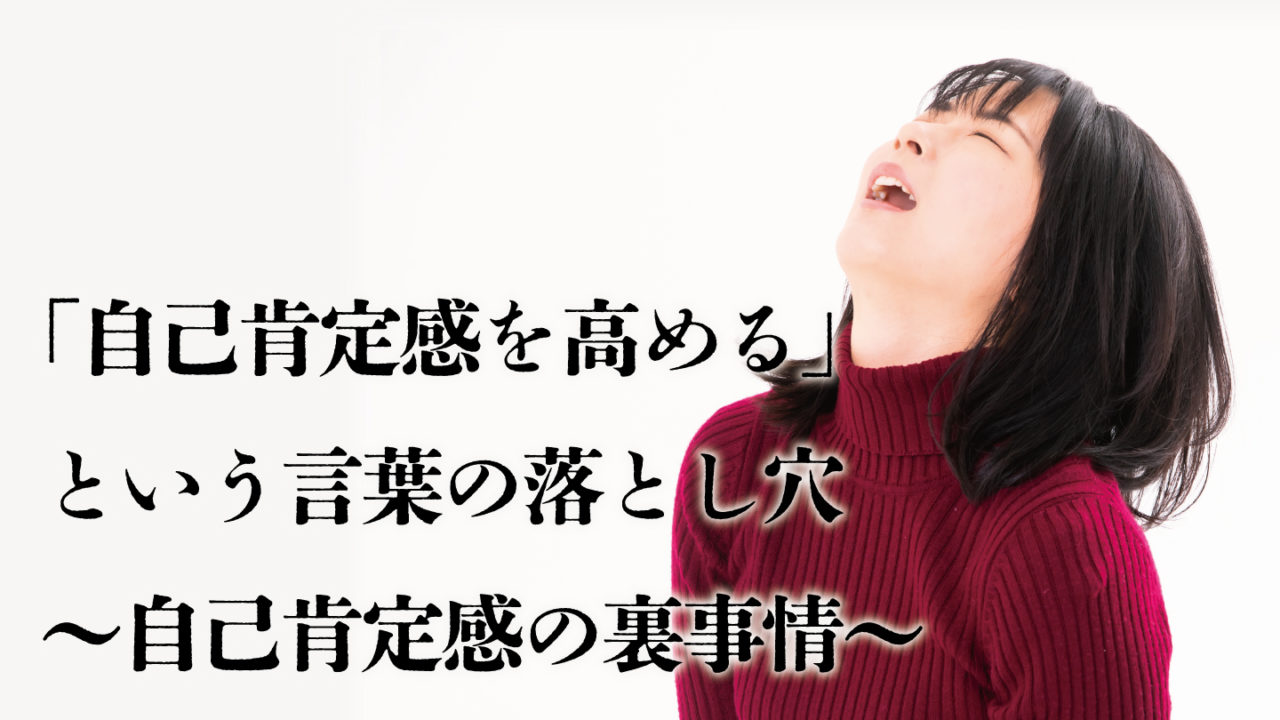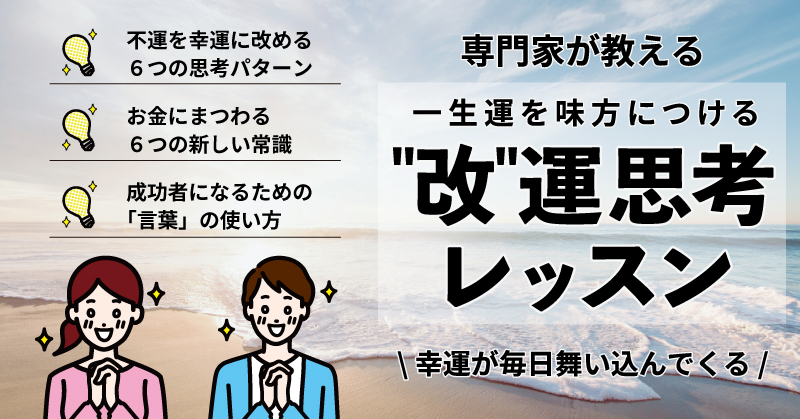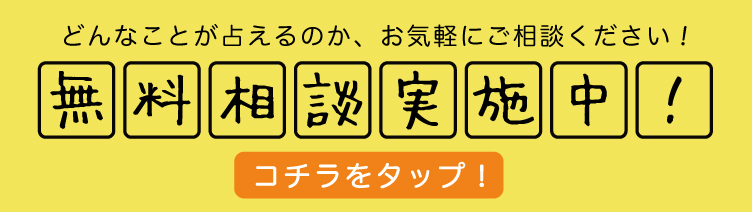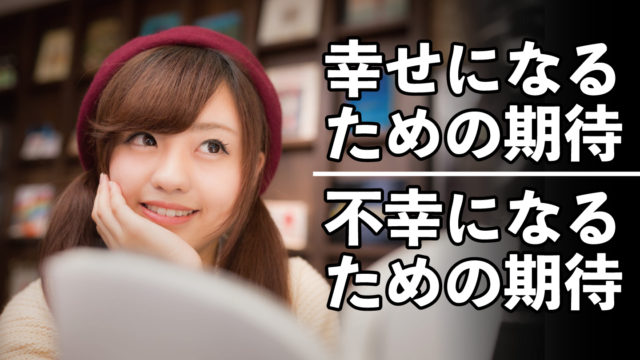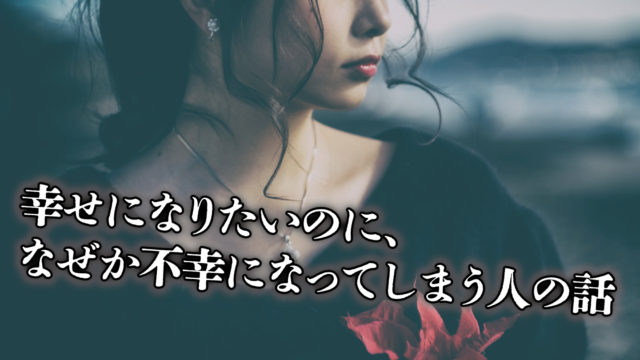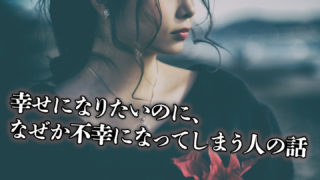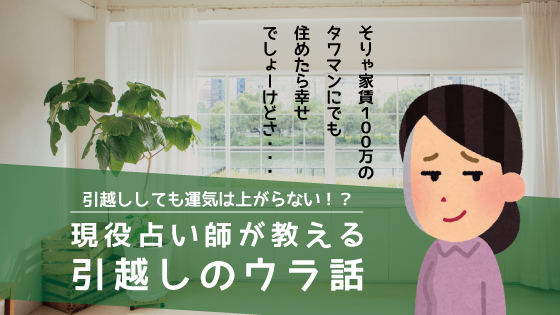どーも。
前田王子です。
現代の占い師にとって、切っても切り離せない言葉があります。
それが
自己肯定感
ここ10年以内くらいで、すっかりおなじみとなったこの言葉。
一度は聞いたことがあるでしょうか?
自己肯定感が低い、自己肯定感が高いなどと言われますが、自己評価でどちらだと思いますか?
占いの現場でもこの言葉は結構出てきます。そして、結構厄介です。
よくあるのは、命式的には(先天的素質としては)自分のやりたいことに忠実なタイプなんですが、環境によって自分のやりたいことを後回しにして育ってしまい、命式と現在地のギャップが広くなってしまった、という人がいます。
この手の方が、いわゆる自己肯定感が低いタイプと言われる人なのですが、
と言ったところで全く響きません。
命式的には、自分のやりたいことがしたい!という欲求を持っているにも関わらず、それをしないがために生きづらくて悩んでいるわけなので、自己肯定感を高くすればいいですよね。
でも、それができない。
そして、いろんなところで「自己肯定感を高めよう!」という言葉だけをみて、高まらない自己肯定感にさらに悩みを膨らませる。
こんな感じの負のスパイラルに陥っている人が結構多いです。
自己肯定感という言葉は一人歩きしているものの、それの取り扱い方が全くわかっていないというのが、自己肯定感という言葉の落とし穴なんだと思います。
イマドキの言葉ってそういう無責任な言葉が多いです。
言葉は分かった上で使おうよ!と思う次第です。
自己肯定のそもそもの話
自己肯定感を高めよう!
なんて言うのは簡単なんですが、じゃあどうしたらいいんだってばよ!って話ですよね。
これ、すっごいそもそもの話
自己肯定感
って言ってるんです。
つまり、「自己肯定してる感じ」を高めようと言ってます。
では聞きますが、
「自己肯定」を意識したことありますか?
自分に対してそこまで肯定したこと、ありますか?
ここがポイントなんです。
そもそもの話、かなり多くの人たち(多分人口の99%くらい)は、「自己肯定」ということをしたことがない、もしくは意識したことがないです。
鏡を見て、髪型いい感じ仕上がったな!とか、いいコーディネートできたな、とかはあるものの、そこに「自己肯定」という言葉は結びつきません。
美味しい料理が作れたとしても、そこに「自己肯定」という言葉は結びつきません。
それに対して「自己肯定感」という言葉は、自己肯定をしたことがある前提で作られた言葉なんです。
自己肯定というのはつまり「普通」
「自己肯定」という言葉がピンとこないのは、「自己肯定」ということを意識したことがないからです。
では、自己を肯定できる瞬間というのはいつでしょうか?
それは、あなたが当たり前に何かをしている時です。
例えば、間違えずに電車に乗ったり、朝起きて遅刻せずに職場に行ったり、いつも通りにシャンプーとリンスを間違えずに使ったりした時です。
つまり、当たり前にこなせているから肯定ができるわけです。
でもそれって、言い換えれば「普通」とか「日常」という言葉なんです。
それを意識的に肯定する、という価値観こそが「自己肯定」です。
対して、
「自己肯定しなければ・・・」
と思い詰めてしまうのは、肯定できないことを肯定しようとするから起こる不具合です。
つまり、一本早い電車で出社して早めに仕事の準備をしようと思ったけど、寝坊してしまった(でも始業には間に合った)とか、毎日日記を書こうと思ったけど、昨日書くのを忘れてしまった(でも今日は書いた)みたいな、自分としては「しまったな〜(肯定はできない)」と思える状況を、肯定しなければ・・・と思うから思い詰める結果になってしまいます。
そりゃそんなことしてたら自己肯定なんてできませんよね。
だって、自分としては肯定できないようなことを捻じ曲げて肯定しようとしてるんだから。
この手の落とし穴にハマって悩んでいる人、非常に多いです。
(かつては僕もその一人でした)
自己肯定の代わりに・・・
「自己肯定感を高めよう」という言葉が理解できないのは、そもそも「自己肯定」をしたことがないからなんです。
それは、ゼロに何を掛けてもゼロになるようなもので、そもそもやったことがないことを上げたり下げたりすることはできません。
では、いわゆる自己肯定感が低いと言われるタイプの方達は、自己肯定の代わりに何をしているかと言うと、
自己否定
という言葉が適切です。
強めの自己否定をしたことなら、たくさん思い当たる節があるんです。
例えば、一本早い電車で出社して早めに仕事の準備をしようと思ったけど、寝坊してしまった(でも始業には間に合った)とか、毎日日記を書こうと思ったけど、昨日書くのを忘れてしまった(でも今日は書いた)といった、そんな些細なタイミングで、
と思ってしまいます。
思い当たる節、ありませんか?
自己肯定感を高めるのではなくて
「自己肯定感を高めよう」という言葉に踊らされて悩み事を増やしてしまっている人は、ビックリするほど沢山います。
占い師という立場で多くの方の悩み事と接してきた僕としては、
ということを提案しています。
結果としてはできなかったとしても、一本早い電車で出社しようと思ったその心意気、すごくないですか?
今回はできなかったとしても、できなかったその一点にフォーカスを合わせるのではなくて、次はどうしたらうまくいくのか、という部分にフォーカスを合わせれば、対策が見えてきます。
そうすることで、自己否定の癖が治まってきます。
自己肯定感難民は多い
昨今の「自己肯定感」という言葉の独り歩きは、なかなかに根深い問題です。
学校教育というものが自己否定感を強める温床になってしまっているので、大人になってふと気がつくと、自己肯定感が低い(自己否定が強い)タイプの人になってしまっています。
テストや通知表で優劣をつけられて、顔やスタイルの良し悪し、運動能力の良し悪しによって、日に日に優劣というのは心の奥底に染み込んでいくものです。
そして、転職サイトなんかのパーソナリティ診断なんかでも「自己肯定感が低い」なんて言われて、どんどん自己肯定感が低いというセルフイメージが刷り込まれていきます。
ですが、人の先天的素質というものは、そんな優劣を望んではいません。
先天的素質は、あなたがあなたでいられることを望んでいます。
自己肯定感難民を抜け出して自分らしい生き方を全うするために、まずは自己否定のクセを見つけて一つずつ止めていってみると、自分がどれだけ自己否定だらけだったのかが分かってビックリします。
現代人って、ホントに自己否定まみれなんですよね。