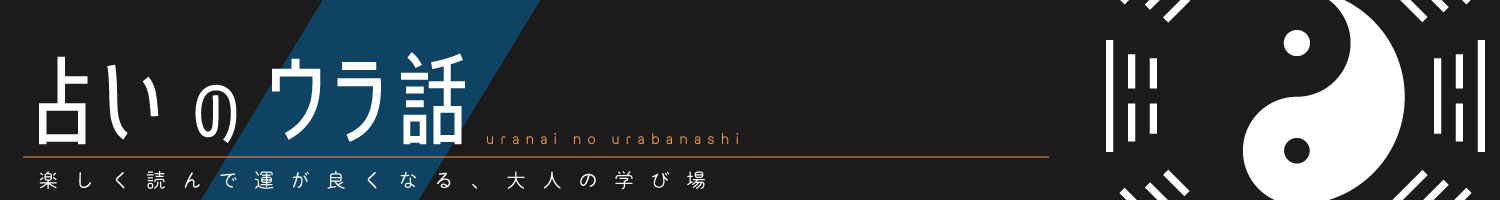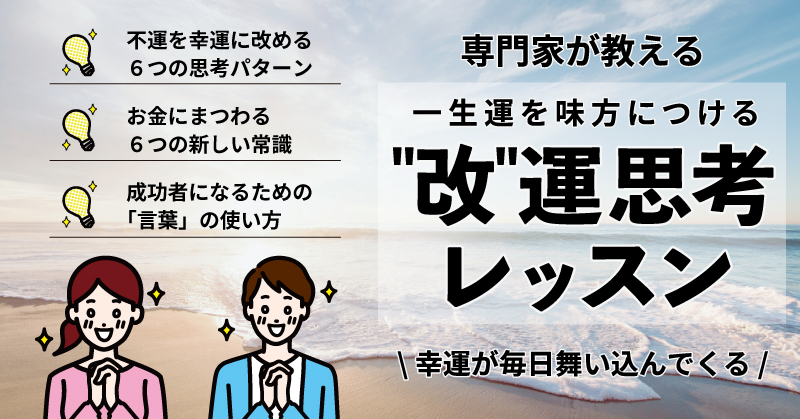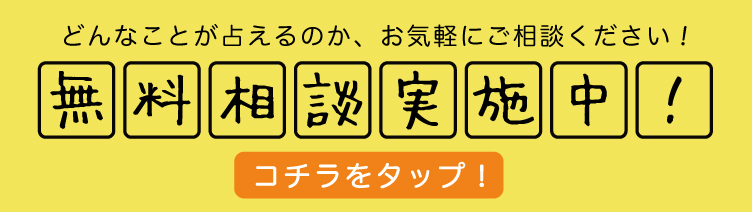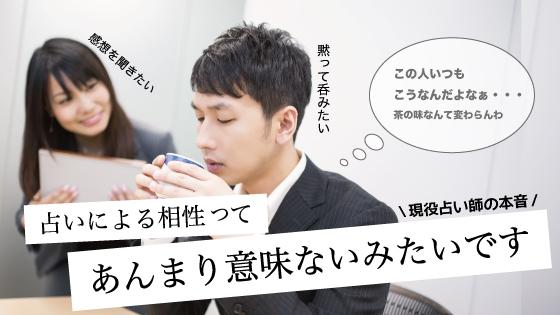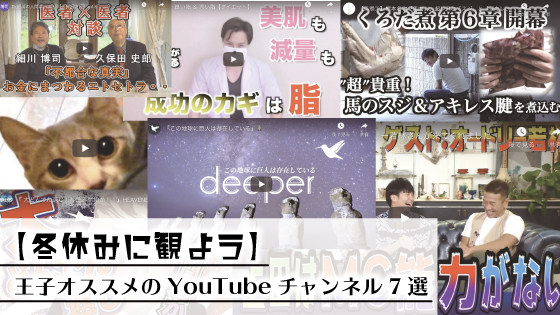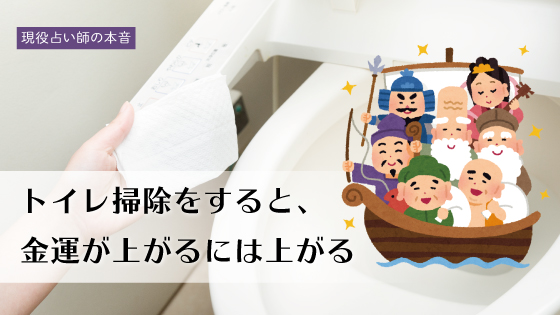どーも。
“改”運トレーナーの前田王子です。
「ホスピタリティ」
という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
サービス業や医療業界、福祉業界などでちょっと前から使われ出した言葉ですね。
ホスピタリティ、つまりは「おもてなし」という意味ですが、この「おもてなし」というのがなかなかどうして非常に難しかったりするわけです。
ですが、人間関係においても、ホスピタリティという考え方を取り入れていくと、非常に円滑にことが進むようになります。
円滑に進むどころか、相手から信頼されたり、任されたり、いい人と思ってもらえたりと、控えめに言って、いいことづくめなんです。
「おもてなし」とは言うものの
ホスピタリティ=おもてなし
と先ほど書きました。
では、「おもてなし」とは一体何なのでしょうか?
言葉としては、「お+もてなす」という構図で、「もてなす」の丁寧語となります。
では、「もてなす」というのは「モノをもって成し遂げる」という語源の言葉です。
現在の使われ方としては、「裏表なし」から転じて、裏表のない心で接客する、という感じになります。
裏表のない心で接客する。
とてもいい言葉ですね。
そして、いい言葉には大体落とし穴があるわけで。
じゃあ裏表がなきゃいいのか、といわれれば、そういうことでもないです。
「おもてなし」という言葉は知っていても、「おもてなし」を体感することってなかなかないです。
と思うシーンは、なかなか無いんじゃないでしょうか。
それはなぜか。
「おもてなし」だと思って行う行為が、実はそんなに「おもてなし」になってない、ということが考えられます。
ここに、ホスピタリティに関する大切なテーマが隠れているわけです。
ホスピタリティの落とし穴
ホスピタリティだと思って、おもてなしだと思って行う行為が、意外と相手に届いていなかった。
そんなことって割とよくあると思います。
その多くは、「良かれと思って」という思想に起因する行動だったりします。
良かれと思ってで行う行為は、実のところ、非常に自分本意な価値観で行われています。
言い換えると、それを行うことで、自分がいい人になろうとする魂胆があるわけです。
もう一つ言い換えると、「ありがとう」のカツアゲとも言えます。
つまり、その行為はホスピタリティではなく、ジャイアン的であって、支配的な考え方に根付いているわけです。
そしてその結果、「こんなにやってあげたのに・・・」という思いが湧いてくることになります。
ホスピタリティの真髄は、相手のためになったかどうか、相手の必要を満たすことができたかどうか、常にここを考えることにあります。
「いい人」になろうとするなかれ
特に、「いい人」にみられたい願望がある人や、「嫌われたくない」と思うタイプの人は、良かれと思ってのホスピタリティをする傾向が強いです。
でもそれは、自分が相手に「いい人」に見られたい、という構図になるわけで、常に自分本意になってしまっています。
いい人に見られたいから、良さそうな行いをするわけですが、それでは本質を見失うことになります。
「いい人」に見られたい、「嫌われたくない」と思う気持ち、それ自体は善良なことなんですが、どうしても主語が「自分が」になってしまいます。
ここに問題があるわけですね。
ホスピタリティという価値観を実践するためには、常に主語は「相手が」になる必要があります。
そして、自分の行動における主語というのは、いつも意識しにくいもので、すぐに隠れてしまうものです。
それ故に、ついつい「良かれと思って」の行動になってしまいます。
ややこしい話ですが、相手にどう思われるかに囚われるのではなくて、自分の行いが、相手にとってどう影響したのか、を常に観察する必要がある、ということです。
なので、ホスピタリティを実践していったとしても、「こんなにやってるのに!」という気持ちにはなりません。
相手からの「ありがとう」をもらうためにやっているのではないですが、相手からの「ありがとう」がいただけなかったとしたら、それは、相手にとって「ありがとう」ではなかった、というだけなんです。
つまり、ホスピタリティの的が外れていた、ということなんです。
だから、相手を観察して、相手の「ありがとう」のポイントを見出す視点が必要なわけです。
そして、その視点こそが「ホスピタリティ」だということです。
ホスピタリティやおもてなしは、行為のことではありません。
あくまで精神的なモノなんです。
ホスピタリティの精神、おもてなしの精神を持っているから、相応の行為が選択できる、ということです。
つまり、相手から「ありがとう」を引き出してやる!という精神ではなく、相手の状況を見て、その意図を汲んで、もし転びそう(困りそう)なら先回りして手を差し伸べる精神のことなんです。
近い言葉としては、滅私奉公とも言えます。
大事なのは、奉公する際には、「私」を滅することなんですよね。
奉公する時の主役は、自分じゃないんです。相手なんです。
だから、そういう行為を受けたときは、素直な「ありがとう」が言えるわけです。
感覚としては、素直な「ありがとう」が口から飛び出したとき、あなたはホスピタリティに出会ったという感じです。
人間関係にもホスピタリティを
ホスピタリティホスピタリティ言ってますが、なにもそれを常時緊張状態で行え!という話ではないです。
感覚としては、ホスピタリティって1%の意識なんだと思います。
決して意識を高くする必要はなくて、自分の思考の1%だけでいいので、相手に向けておくことが大事なんだと思います。
例えば、飲みの席で、空いたお皿を絶妙なタイミングで片付けてくれる人や、絶妙なタイミングでお酒を注いでくれる人がいますが、その人は、飲みの席で空いたグラスばかりに意識が行ってるわけではないですよね。
会話にももちろん参加して、自分自身も楽しんでやっています。
だけど1%だけは、その場に相応しくないモノを排除して、気持ちの良い空間を作ろうという意識に割いているから、そういう行動が取れるわけです。
見習うべきは、この精神なんですよね。
何を隠そう、僕は元々ホスピタリティなんて欠片も持ち合わせていない人です 笑
究極の自己中人間、自分さえ良ければいい、という学生生活を送ってきたので、学生の頃は友達が全然いませんでした。
友達というか、手下みたいな感じの子はいたけど、「友達」と言える人は記憶にほとんどないです。。
そんな人だったので、社会人になってから、めちゃくちゃ怒られました 笑
特に最初はCMの制作会社に入ったので、いわゆるテレビのADみたいなことをしていました。
ADの仕事は、演者や進行の人が、滞りなく撮影を進められるように、その準備を行うことです。
つまりホスピタリティが仕事なようなものなので、かなり鍛えられたとはいえ、最初はもう何をしたらいいのか分からず、何が正解なのかも分からず、超苦痛でした。
でも、先輩や粋な技術さんからいろいろ学んで、少しずつできるようになっていきました。
元々が超自己中なので、未だに自己中が大爆発する時もありますが 笑 (特にお酒の席で)
四柱推命的にも、ホスピタリティの価値観が得意な人とそうでない人は、確かにいるにはいます。
なので、できる人とできない人が存在するわけですが、それでも、1%の意識を心がけることで、成長することができます。
人の心は、練習次第でどこまでも成長することができます。
苦手なところは補って、得意なところはもっと伸ばしていくと、結果的にそれが自信にもつながります。
しかも、経験に基づく、地に足のついた自信になるのでオススメです^^